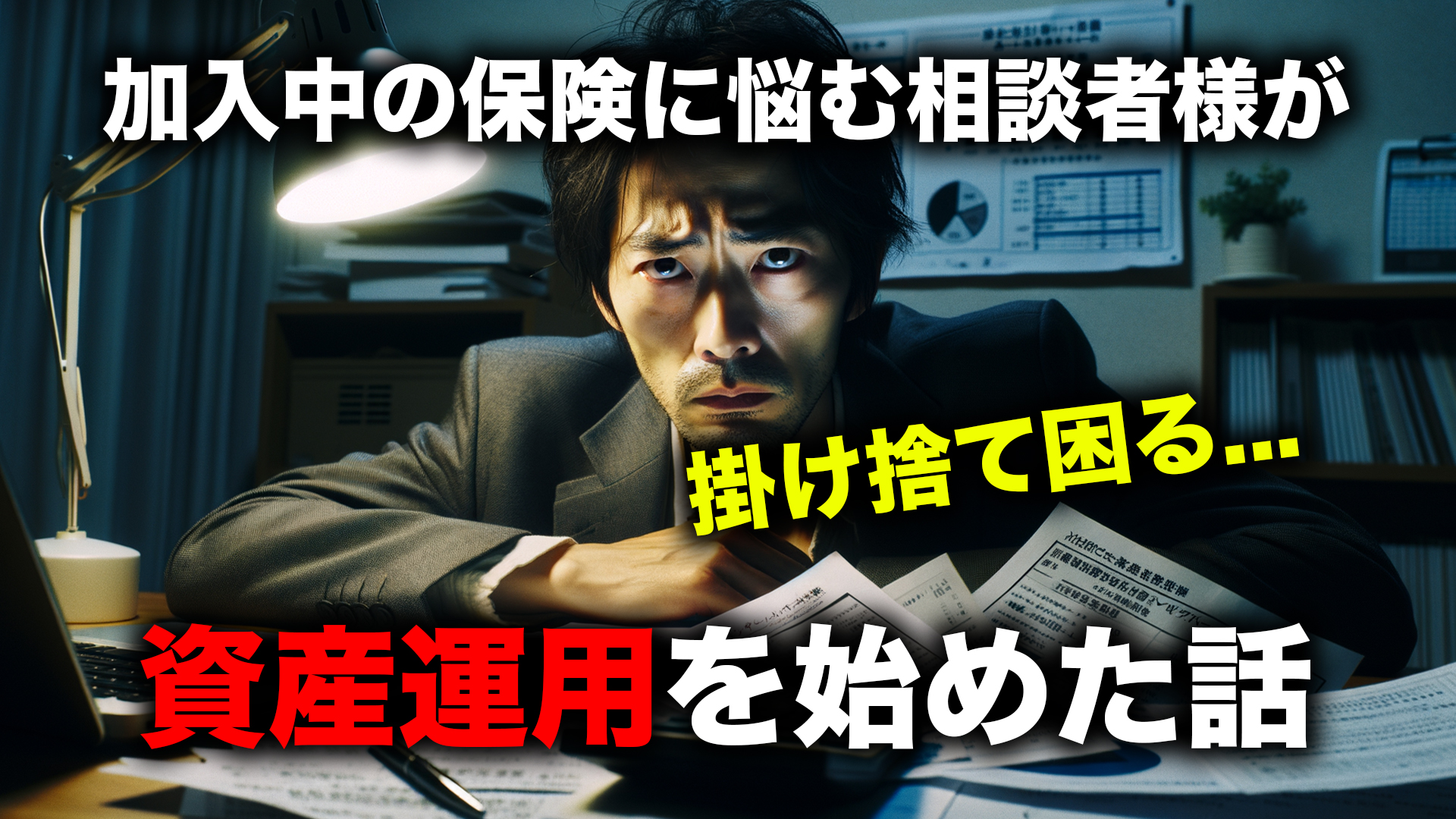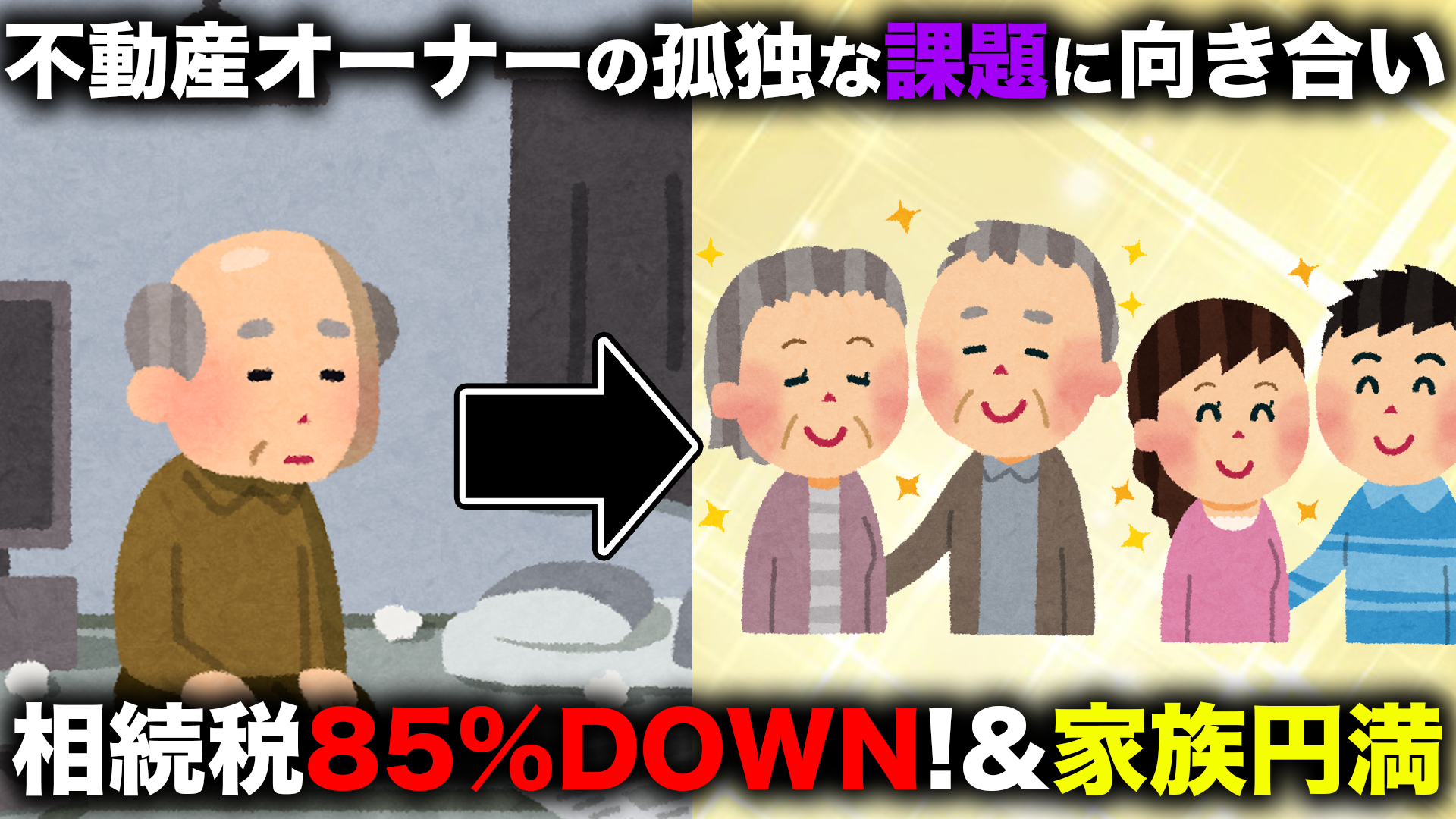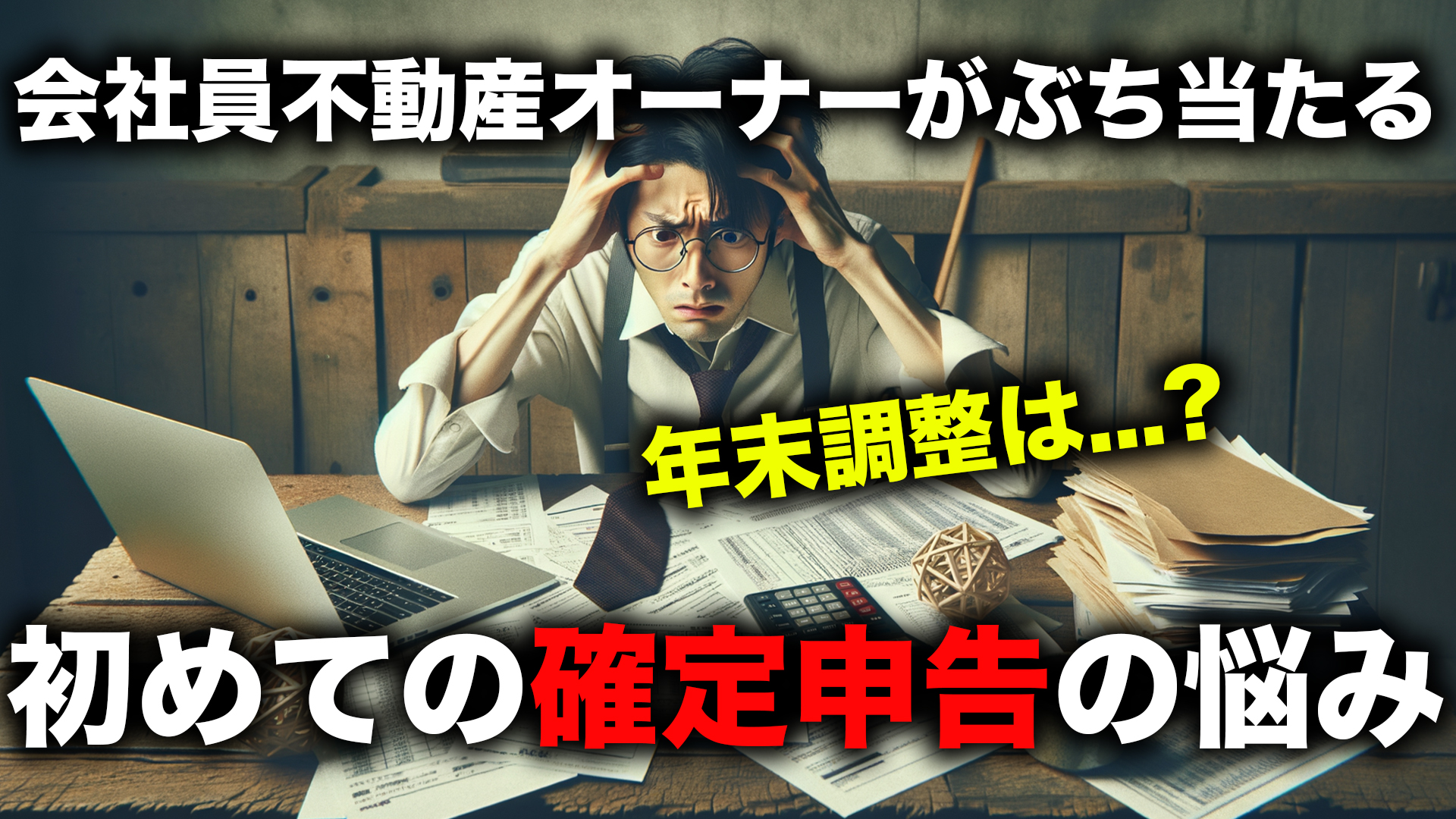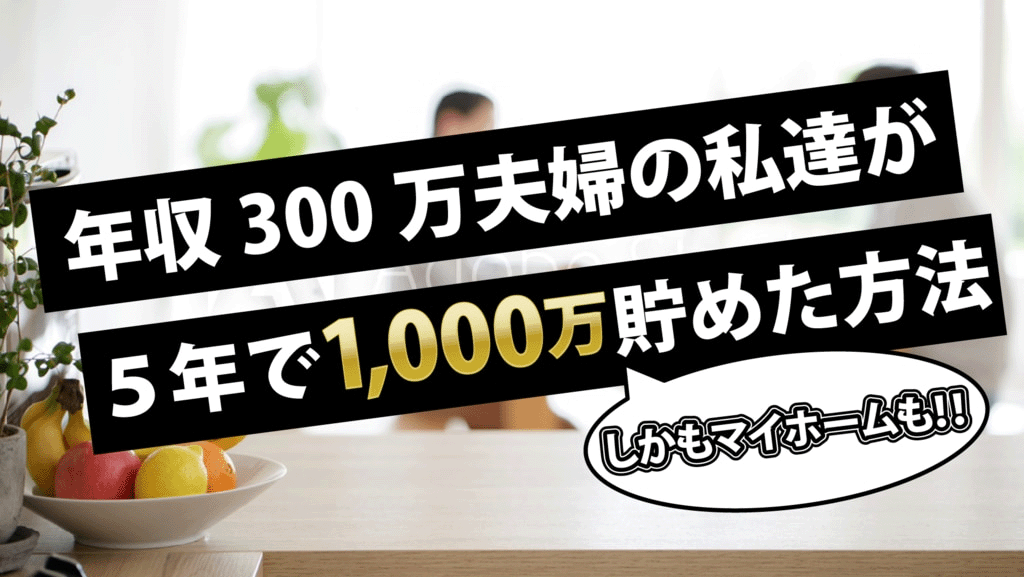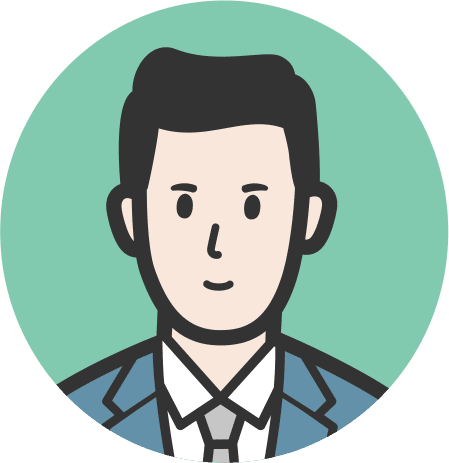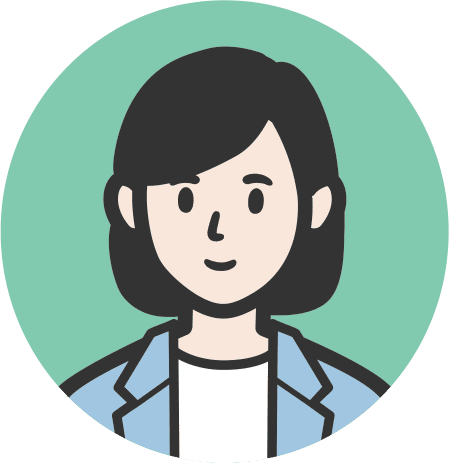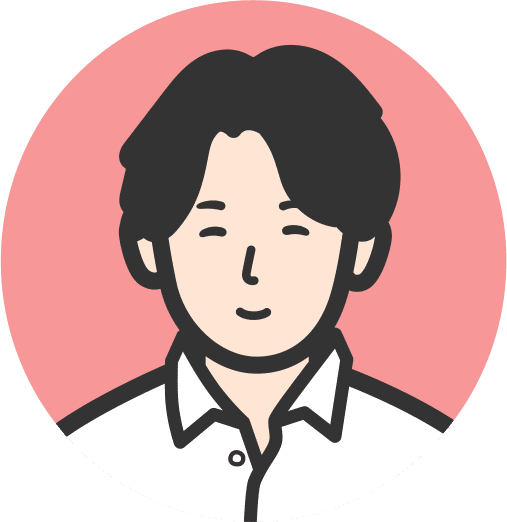ふるさと納税ってどういう制度なの?
地域の名産品などが「お礼品」として届くイメージが強いのではないでしょうか…?
しかし、中にはふるさと納税で損をしている人がいることをご存じですか?!
なんとなく周りがやっているから…友達におすすめされたから…
今回メリット、デメリットを理解していきましょう!
【 目次 】
・ふるさと納税ってなに?
・ふるさと納税に向いてる人
・ふるさと納税のメリット
・ふるさと納税のデメリット
・まとめ
■ふるさと納税ってなに?
ふるさと納税は自分が応援したい自治体に寄付できる税度です。
寄付をすることで、住民税の軽減や税務署から所得税の還付を受けられます。
寄付金の使い道を指定できる上、地域の名産物など魅力的な「お礼品」をいただくことができる仕組みです。
「例えば、10万円をふるさと納税した場合」
10万円が自治体に寄付されます。そうすると寄付した額の30%(寄付した金額の30%以内)今回ですと3万円分相当の「お礼品」をもらうことができます。
残り70%分から2,000円を差し引いた金額が住民税から全額排除されます。今回ですと、6万8000円の税金(一定額が還付・控除)されます。
【寄付した10万円の使われ方】
「お礼品」3万円相当。「あなたが指定した使い道+諸費用」約7万円。
■ふるさと納税に向いている人
ふるさと納税ってだれがやっても得するんじゃないの?!!
実はそうではないんです…損している人も中には…
では、どういう人がふるさと納税に向いているのでしょうか…!?
向いている人
・年収が300万円以上ある会社員(サラリーマン)
・一定以上の所得がある自営業者
大きくこの2つがあげられます。
なぜ、この2つが当てはまるのか…?
その理由をメリット、デメリットを添えて解説していきたいと思います。
■ふるさと納税のメリット
・返礼品が魅力的
・税金が控除される
・キャンペーン・ポイント還元がある
返礼品が魅力的
ふるさと納税の利用者は年々増加傾向にあります。
ふるさと納税の大きなメリット1つ目は、返礼品を受け取れることです。
魅力的な返礼品が多くて悩んでしまいますね…
6万円を寄付した場合は最大1万8,000円分の返戻品をもらえます。またふるさと納税をすることで各地域の特産品や情報を知れるのも大きいです。
税金が控除される
■ふるさと納税ってなに? の 部分でも一度解説しましたが、ふるさと納税を利用すると寄付金額の2,000円を超えた部分に対し、所得税・住民税が控除されます。
ただし、所得税・住民税ともに控除額には上限があるので注意が必要です。また、ワンストップ制度の特例を利用した場合は、所得税から控除は行われず、控除額全額が翌年度の住民税から減額されます。
※ワンストップ制度の特例
確定申告が不要な給与所得者で寄付した自治体の数が5団体以下、確定申告をせずに税額控除を受けられる制度
キャンペーン・ポイント還元がある
ふるさと納税では多種多様なサイトを通して寄付ができるようになっています。サイトによっては新生活応援キャンペーンや周年記念なんかも開催されていたりします。
電子マネーのポイントが付与されたり、ギフト券がもらえたり人気のキャンペーンもあります。
また寄付金はクレジットカードでの支払いも可能で、クレジットカードのポイントも貯めることもできます。
なかには高い還元率のキャンペーンが行われることもあります。
■ふるさと納税のデメリット
・減税や節税ではない…?!
・控除限度を超えると自己負担に…?!
・確定申告が必要…?!
・寄付金が戻ってくるのは…?!
・返戻品を貰えない可能性…?!
ふるさと納税に節税効果はない?!
ふるさと納税は節税になる!!、これ間違いです。
2,000円の自己負担が必要であり、寄付を先に行わなければいけません。
最終的に自己負担を超えた部分が所得税還付あるいは住民税の控除という形で返ってきます。
ポイントとしては、あくまでも「応援したい自治体」にふるさと納税の趣旨になります。結果税制メリットも受けられるという点に注意しましょう。
控除限度を超えると自己負担に…?!
ふるさと納税では、控除限度額を超えた部分はすべて自己負担になるため注意が必要です。
控除限度額は単独世帯、扶養する家族がいる場合で異なってきます。
今回は例として単独世帯の場合控除限度額がどれくらいになるのか見てみましょう。
年収300万円 : 年間2万8,000円
年収500万円 : 年間6万1,000円
年収800万円 : 年間12万9,000円
この限度額を超えてしまうと、寄付をしているだけになってします…
寄付が悪いわけではありませんが、効果を最大限に生かしたい場合は限度額を超えないよう注意しましょう。
確定申告が必要になる場合が…!?
ふるさと納税をすることで税金の還付・控除を受けるには、申告が必要になってきます。
1年間に6自治体に寄付をする場合は自分自身で確定申告が必要になります。
個人事業主や自営業の方には馴染みのある確定申告、会社員の場合は年末調整があるため、確定申告をする必要がない人がほとんどです。
寄付をした自治体から送付される寄付金受領証明書が必要になるので保管しておきましょう。
寄付金が戻ってくるのは…?!
ふるさと納税を行う前に必ず覚えておいてほしいことは、ふるさと納税を行っても税金が調節されるのは翌年からだということです。
限度額は収入になって異なります。
限度額近くまで利用するのは問題ないのですが、税金の還付・控除は翌年です。
上限額が大きい人ほど注意が必要です。
返戻金を貰えない可能性が…?!
ふるさと納税したのに返礼品がもらえない?そんなわけないじゃないか!
意外と知られていないことですが、自分が住んでいる都道府県自治体に寄付をしても返礼品は受け取れません。
自治体は「市町村」都道府県は両方に該当します。
例えば埼玉県春日部市に住んでいる人は「埼玉県」と「春日部市」に該当します。
ただし、返礼品がもらえないだけでふるさと納税自体は可能で控除の対象となったりメリットもあります。
自治体によっては寄付自体ができないところもあるので、詳細は各自治体に確認が必要です。
■まとめ
ふるさと納税には税額控除、返礼品などメリットもあるほか、自分の好きな自治体を支援できるメリットもあります。
ふるさと納税の効果は人によって異なり、これから始める人はなにが自分に最適なのか、限度額を調べることが大切になってきます。
寄附金の支払い方法はポイントが貯まるクレジットカードがおすすめです。
ふるさと納税を検討する際に是非ご活用ください。