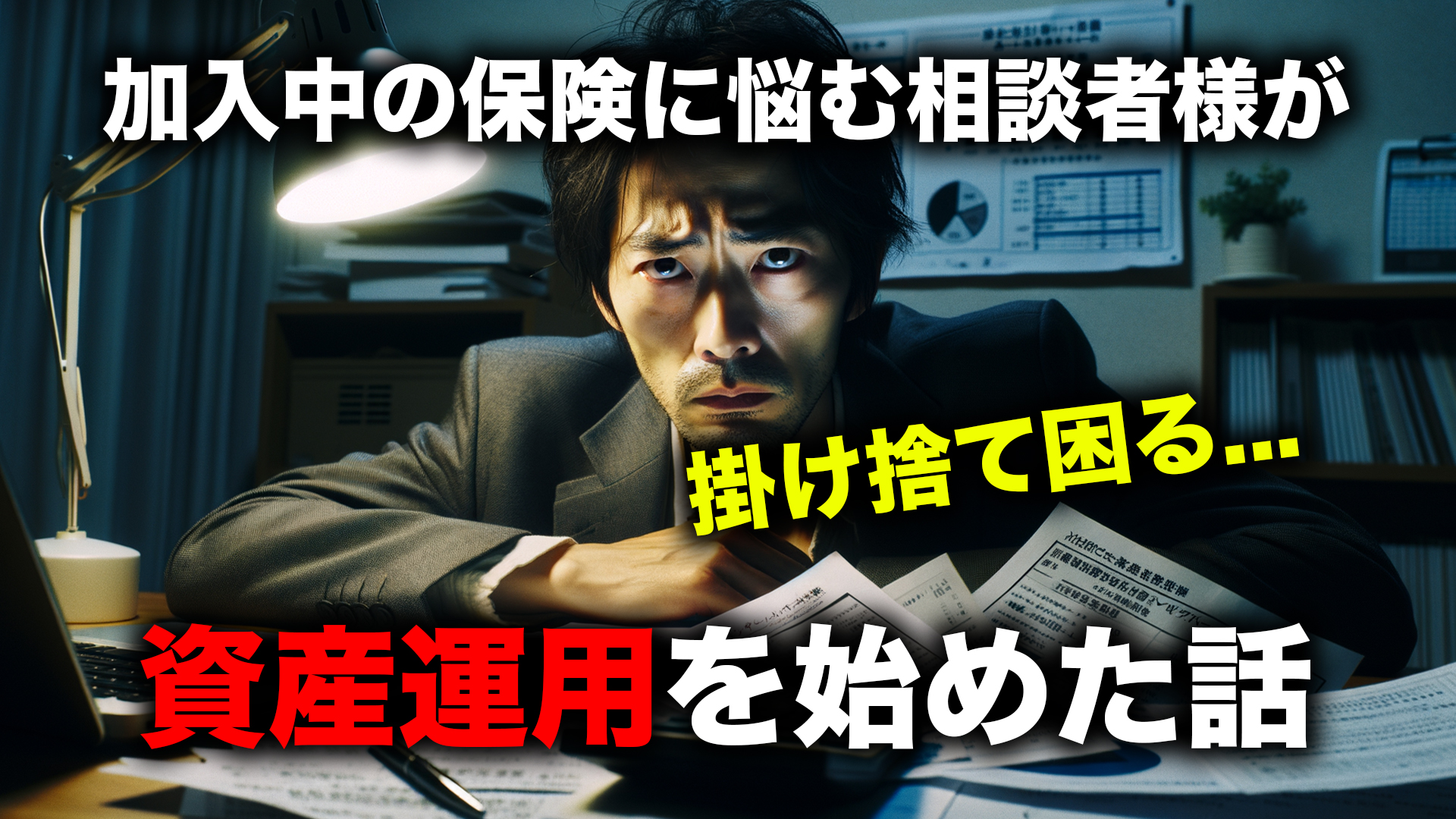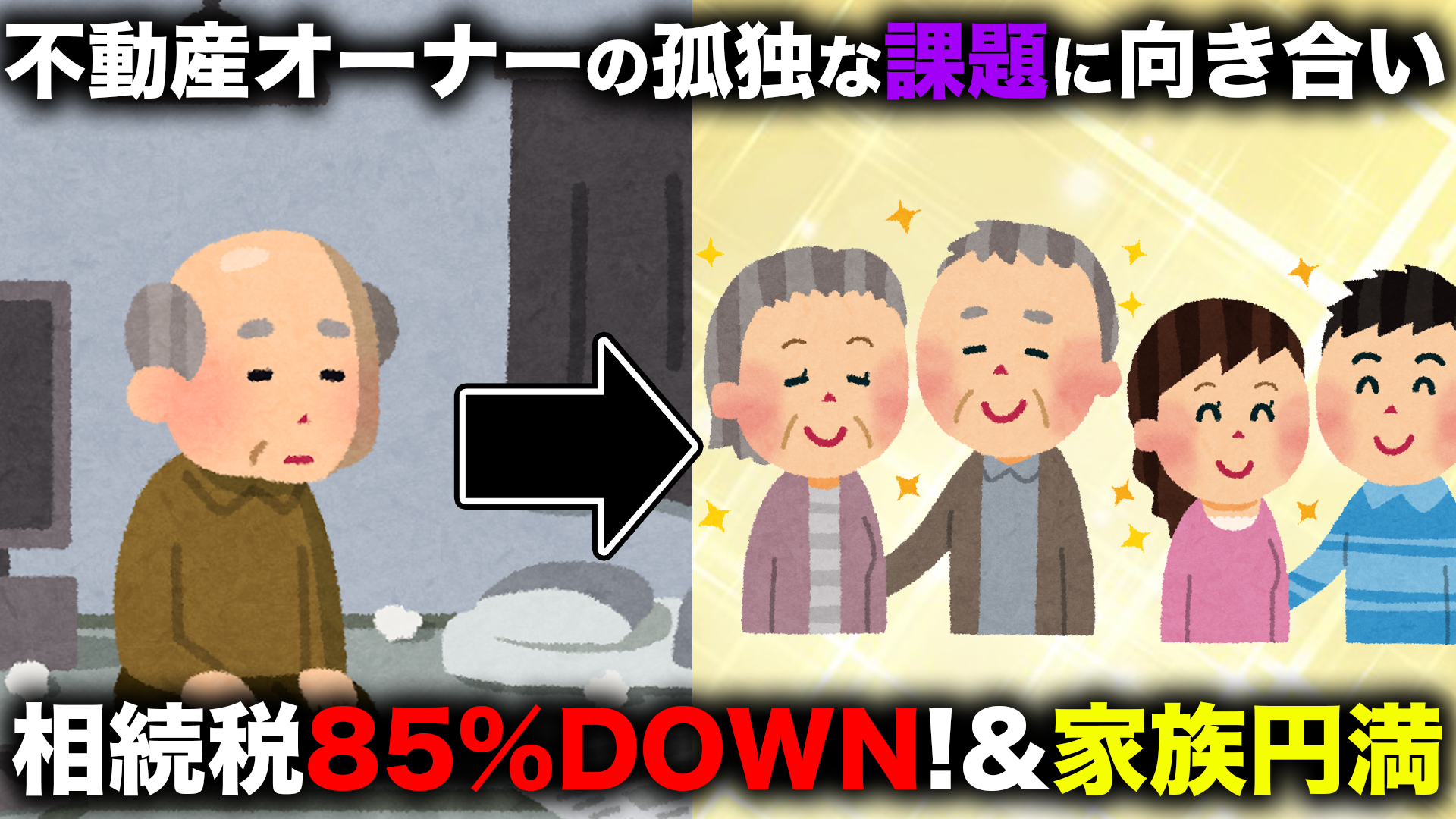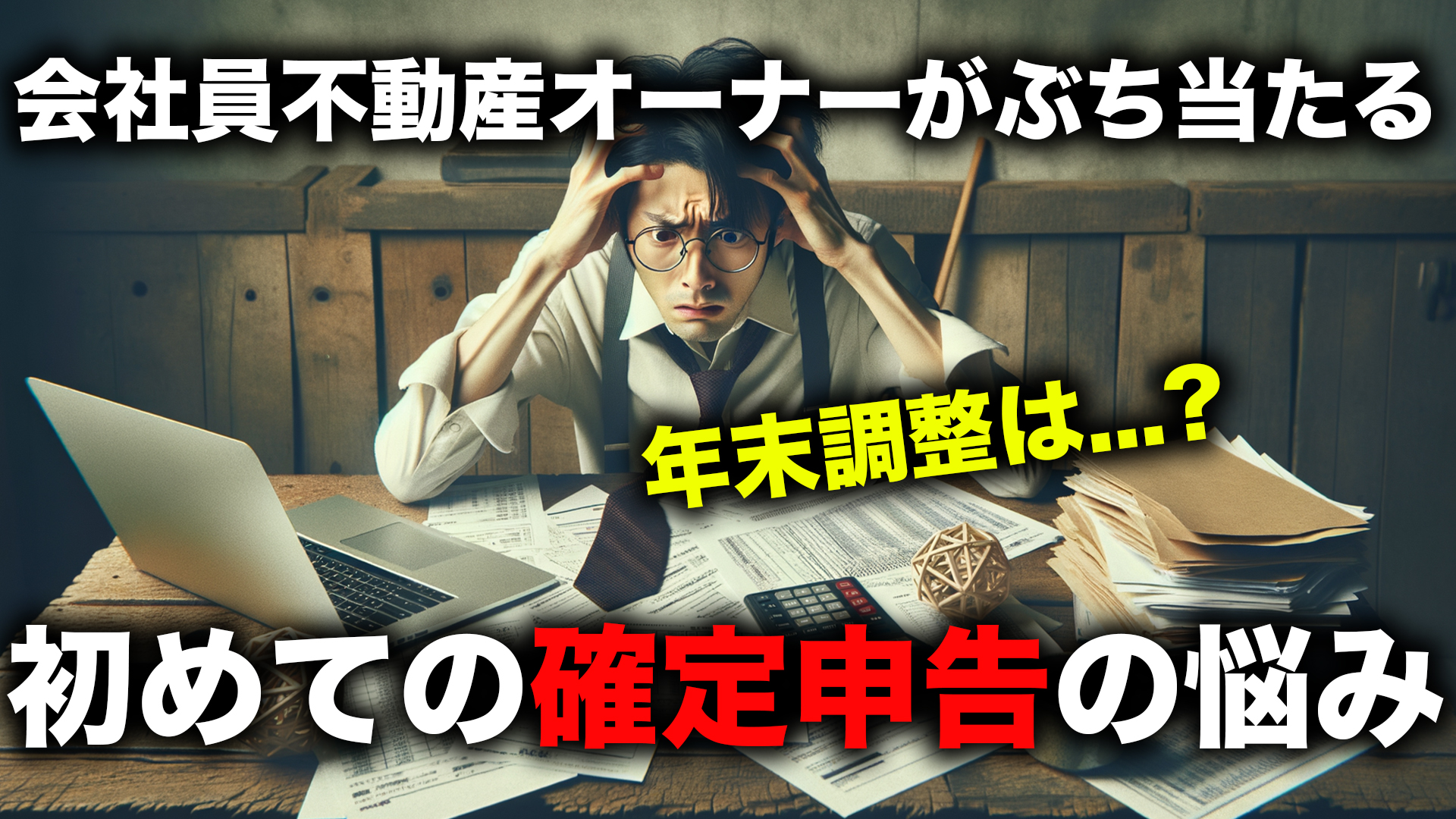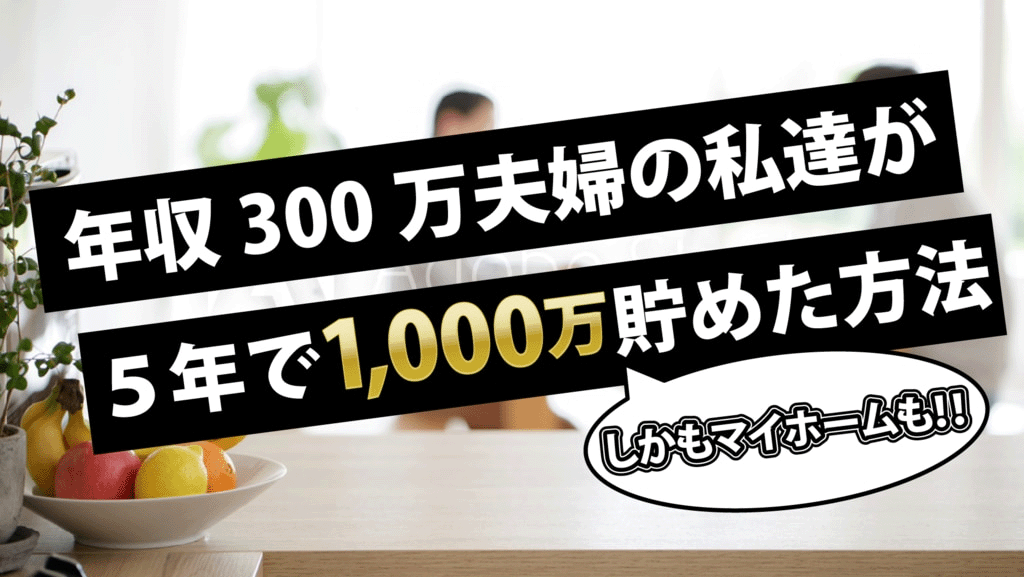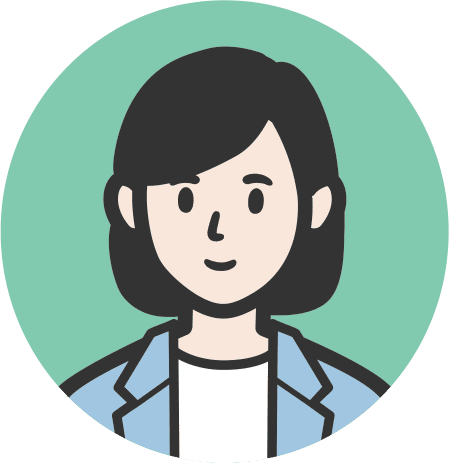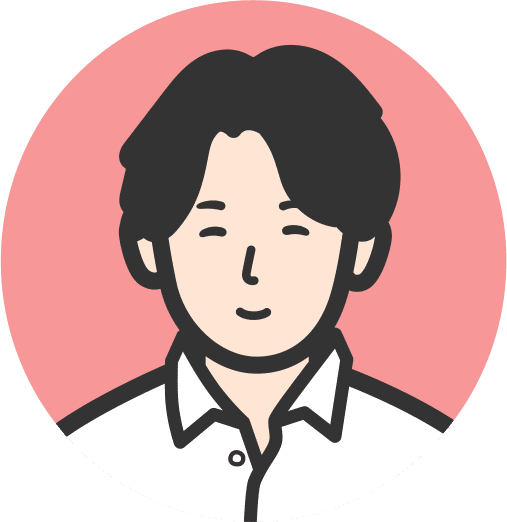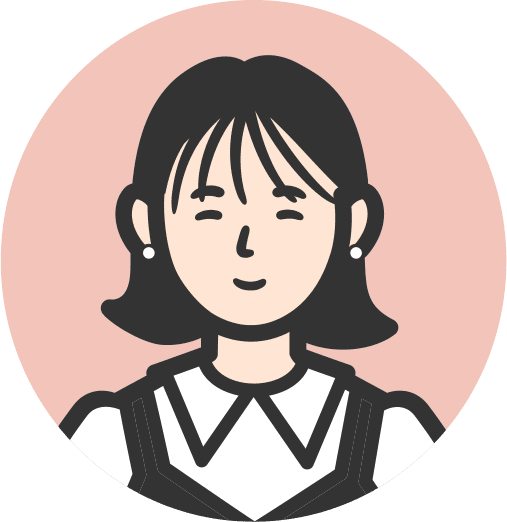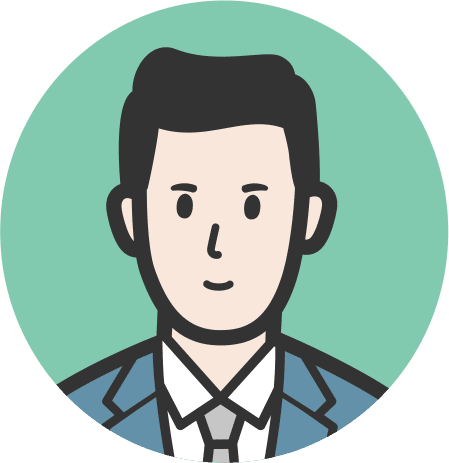気づけばもう年末。
「今年もお金のこと、ちゃんと考えられなかったな…」
そんな気持ちになっていませんか?
実は年末は、たった1〜2時間の見直しで、来年以降のお金が大きく変わるタイミングです。
私はFPとして多くの方の家計相談を受けていますが、
「これ、もっと早く知りたかった…」
という声が毎年必ず出ます。
今回は、FP目線で“年末に必ず確認してほしいお金のポイントをまとめました。
① ふるさと納税「上限額」ちゃんと把握していますか?
「なんとなく毎年やっている」
これが一番もったいないケースです。
✔ 上限オーバー
✔ 控除申請忘れ
✔ 家計全体を圧迫
実際の相談では、自己判断で2〜3万円損している方も珍しくありません。
👉 FPとしては「家計全体の余力」を見て判断します
② iDeCo・NISA、今年分の枠は使えていますか?
年末は「節税のゴールデンタイム」ですが、
無理に使うのはNGです。
大事なのは「あなたの家計に合った金額か?」
投資=正解ではなく、
生活が苦しくなる投資は不正解です。
③ 保険、何年も見直していませんよね?
実は年末の保険相談で一番多いのが
「入った理由を覚えていない」
ライフステージが変われば、必要な保障も変わります。
年末は冷静に整理できる絶好のタイミングです。
④ 医療費控除・各種控除、対象を見逃していませんか?
「え、それも対象なんですか?」
これは本当によく言われます。
✔ 通院交通費
✔ 市販薬
✔ 歯科治療
年末にまとめて整理するだけで、数万円戻るケースもあります。
⑤ クレカ・サブスク、惰性で払い続けていませんか?
家計相談で必ず出てくるのが
「使ってないのに払っているお金」
月2,000円でも、年間24,000円。
10年で24万円です。
⑥ 来年の「大きな出費」把握していますか?
車検・旅行・進学・引っ越し…
お金の不安は「見えないこと」から生まれます。
先に分かっていれば、慌てず準備できます。
⑦ 「誰かに相談する」という選択肢
ここまで読んで「自分の場合はどうなんだろう?」
と思った方は、正常です。
家計はネットの正解より、あなたの正解が大切です。
まとめ
年末は、
✔ 反省の時期
✔ 来年を整える時期
そして、ひとりで抱え込まなくていいタイミングです。
私のFP相談では、
・売り込みなし
・現状整理がメイン
・「今は何もしなくてOK」とお伝えすることもあります
「相談するほどじゃないかも…」
そう思っている方ほど、一度整理すると気持ちが楽になります。